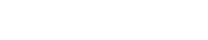BIツールの使い方 ~ 中小企業での具体例

執筆者:カシオ計算機株式会社 三上哲章
BIツール(経営分析ツール)で販売管理データを分析すると、仕入を抜本的に見直して利益を確保するヒントや、営業活動を一工夫して売上をアップできる手がかりが見つかります。
この記事では、私が20年、1,000社以上の中小企業のIT導入に携わるなかで実際に見聞した事例をもとに、活用の具体例をご紹介します。
BIツール(経営分析ツール)なんかいらない?!
「BIツールって大企業が使うものでしょ?うちは車で配達できる範囲で商売しているし、営業部なんてないし、販売状況なんか全部頭に入っているから、分析することなんかない。ただでさえ忙しいから時間の無駄。そんなものいらないよ」
そう思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
「2018年版 小規模企業白書」第2部 第1章 第2節“小規模事業者の経営者の業務負担”を要約すると
- 経営者の1日の実労働時間を見ると、労働時間は9~10時間とする回答が最も多い。全体平均は9時間26分となっており、これは規模が比較的小さい事業所に勤務する一般労働者の平均実労働時間(8時間16分)と比べると長い労働時間になっている。近年の人手不足への対応として「経営者の労働時間を増やし対応」するケースも多く、1週間当たりの平均休日数は「1日」が74.5%と大半を占めており、全体の平均は1.17日となっている。
- 経営者が従事している業務は、「商品やサービスの販売」がもっとも多いが、「在庫管理」「財務・会計(記帳)」「受発注」といった、間接業務を行っている割合も4割を超えている。うち、特に「在庫管理」「受発注」を特に従業員への分担やIT活用により軽減を望んでいて、その負担軽減分は、「売上向上に直接つながる業務に注力したい」と考えている
- 「在庫管理」「受発注」をほとんど電子化できている企業は2割前後にとどまり、残りの8割は”電子化と紙の併用状態”。特に「在庫管理」に関しては5割近い割合で”ほぼ紙での管理”となっている。
となっています。
それで「売上向上(儲け)につながる業務」とはなにか?を考えると、やはり自社の課題をデータに裏付けられた形で把握し、適切な手を打つことだと思います。では、どのような分析が有効でしょうか? こういったときに、P/LやB/Sの集計結果からは読み取ることのできない、BIツールによって販売データを分析することがとても有効なのです。
販売管理データを分析してみよう!
それでは、早速活用シナリオを紹介したいと思いますが、ご覧いただくにあたって前提となる、最低限必要となる三上商店の概要は以下の通りです。
- 神奈川県○×市にある、小規模食肉製造卸売り企業である。
- 得意先は全部で40件。内訳は、飲食店・宿泊施設が30件、給食施設が5件、小規模なスーパーなど小売店が5件。
- 社員は全部で6名。社長、奥様、従業員4名。従業員は朝早くから注文が入っている製品を製造し、配達に行く。社会人として最低限のマナーは身につけさせているが、ルートの配達先で積極的な営業を行うほどのパワーはない。また、社員の状況や自社の設備や供給余力を考えると、現状、大口の新規得意先を開拓する余力はない。
さて、BIツールのセオリーとしての活用手順は、
- まず全体像を掴んで、課題となっている箇所を発見し、
- そこから、課題の詳細をどんどん深堀してポイントを絞っていく
という手順となります。社長はかねてから資金繰りをもっと安定させたいと思っていました。そこで社長は、まず運転資金の根源的な源泉である月別の粗利額の推移を過去にさかのぼって調べました。すると、以前からなんとなくそうは思っていたものの、粗利額は仕入状況に相関していることがはっきりと分かりました。原材料コストが高騰しても、得意先に転嫁することができないためです。そこで社長は次の2点を、対処すべき重要な課題に位置づけました。
- 販売予測の精度を高めて、仕入をもっと効率よく行う
- 自社商品の付加価値アップによる、粗利益率の改善
次に社長は、「販売予測の精度を高めて、仕入をもっと効率よく行うために」月別得意先別の売上状況を調べました。すると、給食施設向けの売上に占める割合が4割近くを占めていて、しかも、毎月安定していることが分かりました。さらに詳細を確認すると、そのなかでも高齢者向けの給食施設2件が特に大口の販売先で、売上の構成商品は、鶏肉が中心となっていて取引数量も非常に安定していることが分かりました。
社長は、給食施設が安定した得意先であることは頭に入っていましたが、商品構成までは把握していなかったのです。長年の取引実績から取引停止のリスクも低いために、従業員に配達などを任せていたということが背景でした。
 EZ販売管理によるBIツールを活用した分析操作イメージ
EZ販売管理によるBIツールを活用した分析操作イメージ 分析を活かして利益と売上をアップ!
従来、三上商店では、基本的に数日~数週間での全社としての商品の売上状況から仕入判断をしていましたが、この発見を元に、鶏肉の仕入について長期契約による定量先物仕入に切り替えることにしました。
また、一連の結果を元に、あらためて社長自身が得意先の「給食施設」に出向いて観察したところ、鶏肉の「油抜き」などの下ごしらえに手間をかけられていることが分かりました。社長は自社での加工時に可能な下ごしらえを請け負う提案を行い、売上のアップも実現することができました。
無料で体験してみよう!
三上商店とその利益改善ストーリーは実際の見聞を組み合わせて作成した架空のものですが、コラム中でご紹介した販売データの分析は、EZ販売管理の経営分析ツール(BIツール)で実際に行うことができます。
EZ販売管理の経営分析ツール(BIツール)は、マウスで気になる箇所をクリックするだけで、気になる事柄をどんどん深堀りできます。データは瞬時に分かりやすくグラフとして表示されます。BIツールがはじめてという方でもカンタンです!