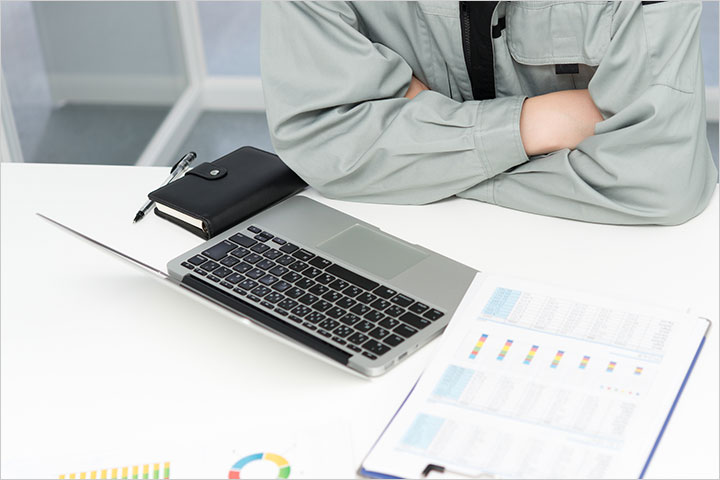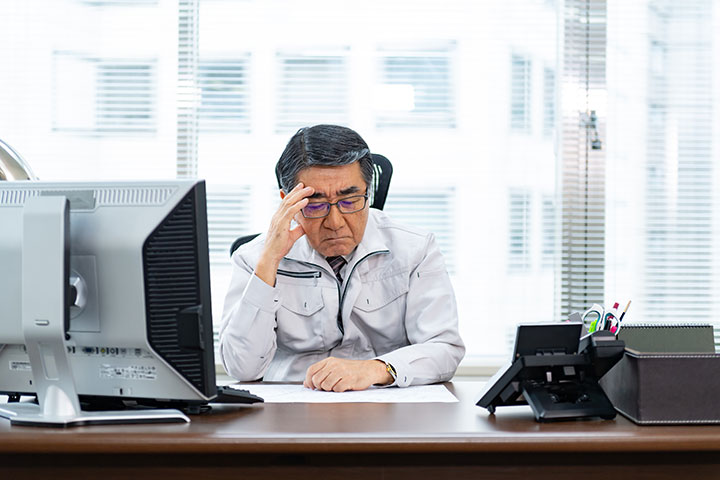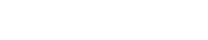知らなかったでは済まされない!働き方改革関連法が中小企業に与える影響とは?

執筆者:株式会社船井総研ITソリューションズ
2019年4月1日より、「働き方改革関連法」が順次施行されます。
「働き方改革」という言葉は既に知っている方が多いかと思いますが、「働き方改革関連法」について、詳しい内容を把握されている方は少ないのではないでしょうか。
今回の「働き方改革関連法」は、企業にとって無視できない内容となっています。特に、中小企業の経営者の皆様は、本法律の施行によって改正される内容をしっかりと把握し、早めの対策を講じる必要があります。
「働き方改革関連法」とは
以下の8つの労働法の改正を行うための法律のことで、正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」です。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
- じん肺法
- 雇用対策法
- 労働契約法
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
上記の法律名を見ても、ピンと来ないかも知れませんが、中小企業の経営者の皆様に知っておいていただきたいポイントをお知らせします。
「働き方改革関連法」の内容
「働き方改革関連法」の施行により、企業が対応すべき主な施策は以下の通りです。
1)有給休暇取得の義務化
有給休暇が年間10日以上ある労働者に5日以上の有給を取得させることを義務化。
2)時間外労働の上限規制
残業労働の上限は月45時間かつ年360時間が原則。
3)「フレックスタイム制」の拡充
労働時間の清算期間を3ヶ月まで延長可能にする。1ヶ月を超える清算期間を設定する場合、労働基準監督署への届出が必要になる。
4)「高度プロフェッショナル制度」の創設
コンサルタントやアナリスト、研究開発業務他、計5職種に従事し、労働時間、休憩、休日の規定を適用せず、割増賃金も無い、年収1075万円以上の社員。
5)「勤務時間インターバル制度」の導入
終業時間から次の始業時間の間に一定時間の休息を設定する。
6)労働時間の客観的な把握の義務づけ
タイムカードやICカード、パソコン使用時間等から客観的な労働時間を記録する必要がある。管理職も対象となる。
7)産業医・産業保健機能の強化
長時間労働者の状況や、従業員の業務の状況など、産業医が従業員の健康管理を適切に行うために必要な情報を提供しなければない
上記、「1)有給休暇取得の義務化」や「2)時間外労働の上限規制」に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という重い罰則を受けます。
また、企業規模によって法律の施行時期が違いますが、「2)時間外労働の上限規制」以外は、企業規模に関わらず、2019年4月より施行されますので、中小企業の経営者の皆様も注意が必要です。
「働き方改革関連法」が中小企業に与える影響
「働き方改革関連法」の施行により、中小企業は以下のような影響を受けることが想定されます。
- 人件費の増大
有給休暇や時間外労働の上限設定により、従来の従業員数では対応出来なくなった業務(時間)をカバーするために、正社員やパート・アルバイトを採用する等、人件費が増加する。 - 管理コスト・手間の増大
従業員の労働時間を客観的に把握することが義務づけられていることや、有給休暇や時間外労働の上限により、無駄な業務を排除し、業務効率をアップさせることが必要になるため、その管理コストや手間が増大する。 - 売上・利益の減少
これまでの従業員数では、今回の法改正の制限を超える時間外労働や、有給休暇の取得義務を満たせない場合、新たな人員を雇用するか、従業員の稼働時間を削減せざるを得なくなり、売上・利益の減少につながる恐れがある。 - 人手不足の深刻化(法令違反の場合)
法改正に対応出来ず、法令違反となった場合、厳罰を受けるだけでなく、企業イメージが悪化し、採用がし難くなったり、従業員の離職率が高まる可能性がある。
上記のような影響を受けないようにするか、最小限に抑えるには、まず、現状の業務を見える化し、そこから無駄な業務を洗い出した上で、その無駄な業務を削減することから取り組む必要があります。
その上で、IT・ツールを使用すれば、さらなる業務の効率化が可能となります。
今回の「働き方改革関連法」施行について、中小企業の経営者の皆様から、「良くわからないし、どう対応して良いかわからない」、「人手不足で採用も出来ないので、残業時間の制限は困る」等の課題やご意見を伺いますが、法律は遵守する必要がありますので、早めに法律の内容を把握し、自社に必要な対策を講じることをオススメします。